「どちらいか」――。徳島や香川を訪れた際や、四国出身の方との会話の中で、この言葉を耳にして「どういう意味だろう?」と首をかしげた経験はありませんか。どこか丁寧で温かい響きはあるものの、標準語にはない独特のフレーズに、返答に困ってしまった方もいるかもしれません。
実際に、徳島県出身の方が感謝の気持ちを込めて「どちらいか!」と返したところ、相手にきょとんとされた、という少し切ないエピソードもあるほどです。

「どちらいか」って、なんだか温かい響きだけど、意味がわからないと返しにくいですよね…。
この記事では、そんな「どちらいか」という美しい方言の謎を解き明かします。単なる言葉の意味だけでなく、その背景にある文化や人々の心、具体的な使い方から意外な語源までを徹底的に掘り下げて解説します。読み終える頃には、あなたも自信を持って「どちらいか」を理解し、その言葉が持つ温かさを感じられるようになっているでしょう。
結論:「どちらいか」の基本的な意味は「こちらこそ」「どういたしまして」

まず結論からお伝えします。「どちらいか」は、主に徳島県で話される阿波弁(あわべん)の一つで、感謝された際の返答として使われる言葉です。標準語にすると、以下の二つの意味合いを持ちます。
- こちらこそ
- どういたしまして
相手から「ありがとう」と言われた時に、「いえいえ、こちらこそありがとうございます」という、感謝を返すニュアンスで使われるのが特徴です。単に「お礼には及びません」と謙遜する「どういたしまして」よりも、相手への感謝や敬意を返す気持ちが強く込められており、非常に丁寧で心温まる表現と言えるでしょう。
ある料理店では、「こちらこそ、どうもありがとうございます」という感謝の気持ちを忘れないために、この言葉を店名にしたという素敵な話もあります。

なるほど!ただの「どういたしまして」じゃなくて、もっと心がこもった言葉なんですね!
「どちらいか」の意味早見表
| 方言(Dialect) | 標準語(Standard Japanese) | 英語のニュアンス(English Nuance) |
| どちらいか | こちらこそ | "Likewise," "The pleasure was all mine" |
| どちらいか | どういたしまして | "You're welcome," "Don't mention it" |
| どちらいか | (感謝の返答として) | 相手の感謝を受け止め、自分からも感謝を返す丁寧な表現 |
【実践編】「どちらいか」の具体的な使い方と会話例文
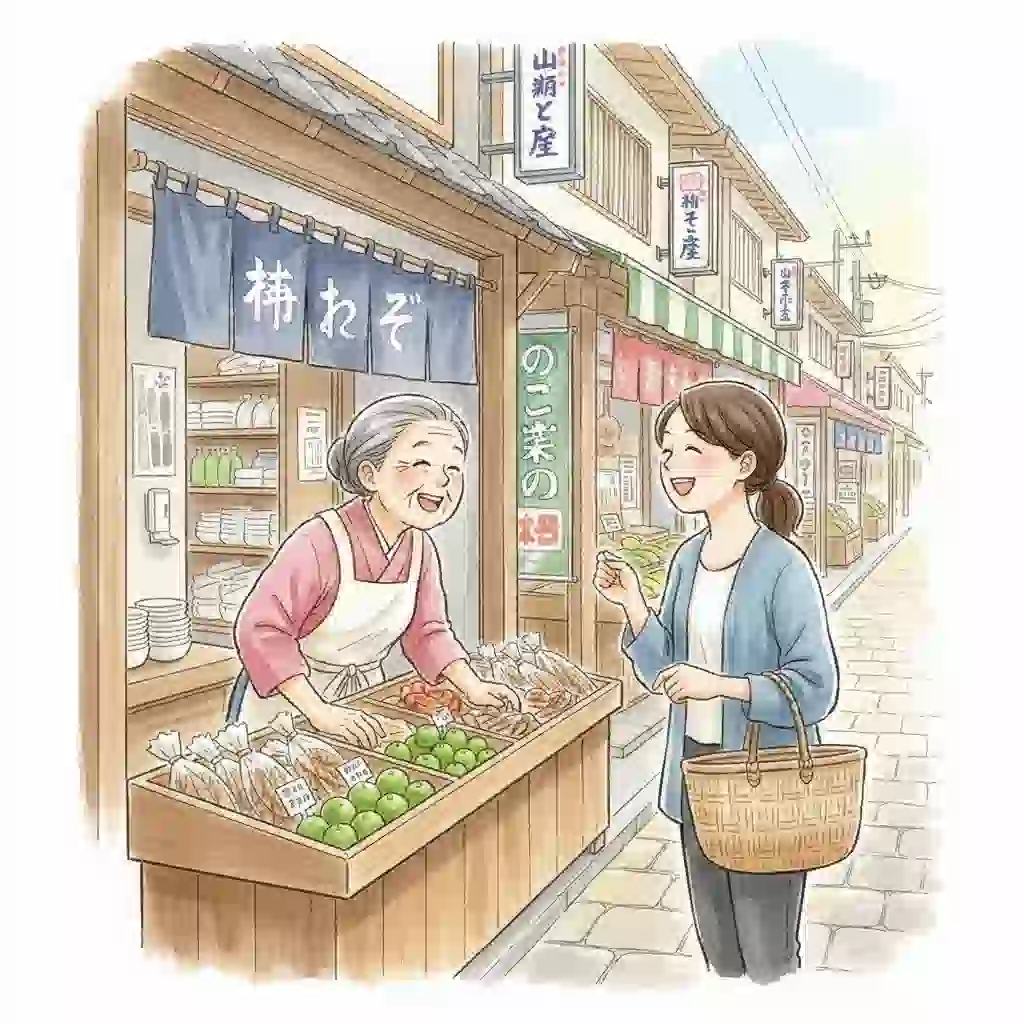
「どちらいか」がどのような場面で使われるのか、具体的な会話例を通して見ていきましょう。この言葉が持つ温かい雰囲気をより深く理解できるはずです。

具体的にどんな風に使うのか見てみたいな!
最も一般的な使われ方は、相手からのお礼に対する返事です。例えば、何か手伝った翌日に「昨日はありがとうございました」と言われた際に、「いえいえ、どちらいか」と返します。また、電話の終わり際に「ありがとうね!」と言われた時の締めの一言としても自然です。(参考:阿波弁講座|つるぎええとこ.com)
場面別「どちらいか」会話シミュレーション
徳島を旅行した際や、阿波弁を話す方とのコミュニケーションで役立つ会話シミュレーションをご紹介します。
| 場面(Situation) | Aさんの言葉(標準語) | Bさんの返答(阿波弁) | Bさんの言葉の意訳 |
|---|---|---|---|
| お土産を渡した時 | 「素敵なプレゼント、本当にありがとう!」 | 「いえいえ、どちらいか。喜んでもらえて嬉しいわ。」 | 「とんでもない、こちらこそ。喜んでもらえて嬉しいです。」 |
| 仕事で手伝ってもらった翌日 | 「昨日は遅くまで手伝ってくれて助かりました。」 | 「どちらいか。こっちも勉強になったけん。」 | 「こちらこそ。私の方も勉強になりましたから。」 |
| 道を尋ねてお礼を言う時 | 「親切に教えてくださり、ありがとうございました。」 | 「どちらいか。気ぃつけてなー。」 | 「どういたしまして。気をつけてくださいね。」 |
| 電話の終わり際 | 「じゃあ、また連絡するね。色々とありがとう!」 | 「はいよー、どちらいか。ほな、また。」 | 「はい、こちらこそありがとう。それでは、また。」 |
このように、「どちらいか」は日常の様々な感謝の場面で、人間関係を円滑にする潤滑油のような役割を果たしているのです。
「どちらいか」はどこの方言? 徳島・香川で使われる阿波弁の魅力
「どちらいか」は、主に徳島県(旧阿波国)で使われる阿波弁です。徳島市内を中心に広く使用されているとされています。また、地理的に隣接する香川県でも使われることがあります。
意外な事実:北海道でも使われる?人の移動と方言の旅

興味深いことに、「どちらいか」は北海道の方言としても知られていることがあります。しかし、そのルーツは阿波弁にあると考えるのが妥当です。
阿波弁は関西弁の親戚?
阿波弁は四国方言に分類されますが、その中でも特に近畿方言(関西弁)の影響を最も強く受けているという特徴があります。これは、徳島が地理的に近畿地方に近く、古くから海上交通などを通じて文化的な交流が盛んであったためです。
例えば、阿波弁で「疲れた」を意味する「しんだい」は、関西弁の「しんどい」と非常によく似ています。このように、阿波弁を知ることは、関西弁との繋がりや日本語の方言全体の系統樹を理解する上でも非常に面白い視点を提供してくれます。
【深掘り】「どちらいか」の語源は? 古語との関連を探る
このユニークな響きを持つ「どちらいか」は、一体どこから来たのでしょうか。その語源を探ると、日本語の古い形が見えてきます。

え、てっきり「どちらか」がなまったのかと思ってた!
最有力説:「どちらへか」が変化したという説

最も有力な説は、古語の「どちらへか」が音便化(発音しやすく変化)したもの、というものです。
古い言葉の使い方を調べると、「どちらへか」は「どういたしまして」「お互い様です」という意味で、感謝や謝罪への返答として使われていた記録があります。(参考:Weblio辞書)
「こないだすまなんだの」
「いやいやどちらへか」
(訳:「この間は悪かったね」「いえいえ、どういたしまして」)
この「どちらへか(dochira e ka)」という発音が、時代を経て「どちらいか(dochiraika)」へと滑らかに変化したと考えるのは非常に自然です。意味も用法も現代の「どちらいか」と完全に一致しており、これが語源である可能性は極めて高いと言えるでしょう。
もう一つの可能性:古語の疑問詞「いか」の影響
もう一つ、より深く言語学的に考察するならば、言葉の末尾にある「いか」の部分が、古語の疑問詞「いか(如何)」と関連している可能性も考えられます。
「いか」は「どのように」「どうして」といった意味を持つ言葉で、「いかが」「いかでか」などの形で使われます。もしこの「いか」のニュアンスが含まれているとすれば、「どちらいか」は文字通りには「(私の方こそ感謝すべきなのに)どうしてこちらがお礼を言われる側でしょうか」という反語的な問いかけになります。
この解釈は、「いえいえ、お礼を言うべきはむしろ私の方です」という「こちらこそ」の謙虚な気持ちを完璧に表現しており、言葉の奥深さを感じさせます。
【観光・学習者向け】徳島ツウになれる!「どちらいか」以外の面白い阿波弁
「どちらいか」を覚えたら、他の阿波弁も使ってみたくなりませんか? 徳島への旅行や地元の方との交流が何倍も楽しくなる、ユニークで便利な阿波弁をいくつかご紹介します。
すぐに使える!阿波弁便利フレーズ集
| 阿波弁(Awa-ben) | 意味(Meaning) | 使い方・豆知識 |
|---|---|---|
| あるでないで | あるじゃないですか | 「あるの?ないの?」と混乱を招くことで有名な阿波弁の代表格。「ここにペン、あるでないで」は「ここにペンがあるじゃないか」という意味。 |
| せこい | 苦しい、しんどい | 【最重要注意】標準語の「ケチ」とは全く意味が異なります。「今日の仕事はせこかった」は「今日の仕事はしんどかった」という意味です。 |
| ごっつい | すごい、とても | ポジティブな意味で使われる強調の言葉。「ごっついラーメン」は「すごい(美味しい・大きい)ラーメン」という意味になります。 |
| しんだい | 疲れた | 関西弁の「しんどい」とほぼ同じ意味で、近畿方言からの影響がうかがえます。 |
| ほなけんど | だけど、しかし | 会話の接続詞として頻繁に使われます。「ほなけんど、〜」と自然に言えれば、あなたも阿波弁マスターに一歩近づきます。 |
| まける | (液体が)こぼれる | 「水がまけまけじょ」と言うと「水が溢れそうなくらい一杯だよ」という意味になります。言葉の響きが面白い表現です。 |
| いける? | 大丈夫? | 体調を気遣う時などに「おまはん、いけるん?」のように使います。シンプルで覚えやすい言葉です。 |
文化の中の「どちらいか」:店名から伝わる感謝の心
「どちらいか」は、単なる方言の語彙としてだけでなく、その地域の文化や価値観を象徴する言葉として今も生き続けています。
香川県高松市には、「季節料理どちらいか」という和食店があります。店主は、店名について「お客様はもちろん、食材やその作り手の方などへの感謝を忘れず、精進してまいりたい」という思いを込めて名付けたと語っています。この言葉が持つ「こちらこそ、ありがとう」という相互の感謝の精神が、お店の哲学そのものになっているのです。(参考:季節料理どちらいか 公式サイト)
また、前述の通り、ある大学の学長が曾祖母の使った「美しい方言」として「どちらいか」を記憶しているように、この言葉は世代を超えて家族の温かい記憶と結びついています。
これらの例は、「どちらいか」が辞書の中の言葉ではなく、人々の心の中で大切に受け継がれ、感謝と思いやりの文化を伝える役割を担っていることを示しています。
まとめ
もし徳島や香川を訪れる機会があれば、ぜひ耳を澄ましてみてください。そして、誰かに親切にしてもらった時には、少し勇気を出して「どちらいか」と返してみてはいかがでしょうか。きっと、その一言が地元の方との心の距離をぐっと縮めてくれるはずです。
本記事は公式サイト・各サービス公式情報を参照しています
